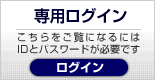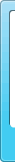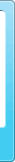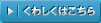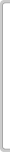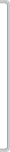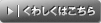静岡県職員組合
〒420-8601
静岡県静岡市葵区追手町9番6号
静岡県静岡市葵区追手町9番6号
県庁本館1F
TEL.054-221-2186
FAX.054-221-3574
TEL.054-221-2186
FAX.054-221-3574
共済部(各種保険・共済)
TEL.054-221-2192
139496
私たち静岡県職員組合(略称:静岡県職)は、静岡県職員で組織している労働組合であり、現在の組合員数は約4,400名です。別に静岡がんセンター労組(約800人)、県社協労組(約20人)、静岡県立病院労組(約1,750人)があり、4労組を合わせて静岡県関係職場労働組合連合(略称:静岡県職労)を構成しています。
私たちの賃金や労働条件は労使交渉により決定しています。賃金・労働条件については個々の職員では対応できないことが多く、結果として労働者の権利が侵害される場合も多々あります。静岡県職は組合員を代表して交渉を行い、賃金・労働条件の維持・改善を図るとともに、組合員の権利を守れるよう力を合わせて取り組んでいます。
私たち静岡県職は、自治労にも加入し、全国の地方公務員労働者の仲間とともに、さまざまな課題に取り組んでいます。
私たちの賃金や労働条件は労使交渉により決定しています。賃金・労働条件については個々の職員では対応できないことが多く、結果として労働者の権利が侵害される場合も多々あります。静岡県職は組合員を代表して交渉を行い、賃金・労働条件の維持・改善を図るとともに、組合員の権利を守れるよう力を合わせて取り組んでいます。
私たち静岡県職は、自治労にも加入し、全国の地方公務員労働者の仲間とともに、さまざまな課題に取り組んでいます。
静岡県職員組合からのお知らせ
静岡県職員組合からのお知らせ

|
2024-02-10 | 県職ニューストピックス2月号掲載 |

|
2024-01-10 | 県職ニューストピックス1月号掲載 |

|
2023-12-10 | 県職ニューストピックス12月号掲載 |

|
2023-11-10 | 県職ニューストピックス11月号掲載 |

|
2023-10-10 | 県職ニューストピックス10月号掲載 |